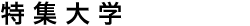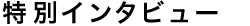人物重視の教育を実践
甲南大学

人物重視の教育を実践
人文、自然、社会科学系にまたがる8学部14学科を持つ総合大学ながら1学年約2千人というミディアムサイズの強みを生かして一人一人の才能を引き出し、人物重視の質の高い教育を実践している甲南大学。キャンパス内の融合を促し、地域、世界へつながる仕組みがふんだんに用意され、その刺激から生み出される学生たちの自主的な学びが、卒業後の伸びしろをつくっている。
地域連携、ボランティア盛んに 社会で必要な能力培う
自治体、企業とのコラボ続々
 地域連携センター主催の「ボラ活」。ボランティアを希望する学生と地域の団体を結びつけるマッチングイベント
甲南大学地域連携センター(KOREC)の活動が充実の一途をたどっている。学生ボランティアの活性化を主な役割にしてきたが、昨年、広範な地域連携を推進するために体制を強化し、新たな一歩を踏み出した。自治体、企業、商店街などと連携し、学生が参加できる地域活動の幅が広がりを見せている。
地域連携センター主催の「ボラ活」。ボランティアを希望する学生と地域の団体を結びつけるマッチングイベント
甲南大学地域連携センター(KOREC)の活動が充実の一途をたどっている。学生ボランティアの活性化を主な役割にしてきたが、昨年、広範な地域連携を推進するために体制を強化し、新たな一歩を踏み出した。自治体、企業、商店街などと連携し、学生が参加できる地域活動の幅が広がりを見せている。
例えば大学近隣の岡本商店街振興組合と、梅の名所であることに着目した「岡本梅紅茶」を共同開発。学生がオープンキャンパスなどで試飲アンケートを繰り返し、商品化を実現した。
 甲南大学と加古川市がタッグを組み、地元企業の課題解決
甲南大学と加古川市がタッグを組み、地元企業の課題解決
に取り組んだ
また「加古川『知』を結ぶプロジェクト~行政・大学・地元メディアによる地域の課題解決」を実施。4ゼミ7チームが加古川市の企業課題の解決を提案した。今年はこれらの活動を発展させるとともに、他地域への展開も計画している。
「学内の学びだけでは得られない、社会人として必要な経験や能力を、地域の方との関わりを通じて身に付けてほしい」と同センター所長で文学部歴史文化学科教授の佐藤泰弘さん。地域連携への取り組みは、「人物教育」という大学の教育ビジョンを実現する場となっている。
学生ボランティアでは、被災地復興支援やチャイルドフェスティバルの企画など、従来から継続する取り組みに加え、新しい試みも始まっている。
5月13日に開かれた「ボラ活」。NPO、自治会など地域団体と、クラブ、サークルなど学生団体とを結びつけるマッチングイベントだ。まだ2回目であるが、参加した地域団体の数は倍増している。甲南大生と地域の絆はますます強まりそうだ。
進路把握率99.3%を達成 懇談会や職場見学など豊富に
 卒業生とカレーを食べながら就活体験を聞く懇談会。
卒業生とカレーを食べながら就活体験を聞く懇談会。
甲南のOB・OG積極的に在校生のキャリア支援に協力
してくれる
キャリアセンターは、学生の就業意識を高める「キャリア教育」、就職をサポートする「キャリア支援」を二つの柱に学生一人一人の能力や適性を把握し、それぞれの目標、夢をサポートしていく。
1年次から自分のキャリアを考えるセミナーを「ハレ晴れセミナー」と銘打って開催している。国家資格を持つ人たちを招いて資格取得までの過程などを相談できる懇談会や、実際に職場を見学して将来の進路について考える会社見学ツアーも用意されている。3、4年次にもキャリアを考える講座・授業科目が組み込まれている。
卒業生が就職をサポートしてくれるのは母校愛の強い甲南大学ならでは。1、2年次の学生と甲南大学を卒業して間もない先輩が、カレーを食べながら、仕事のやりがいや、就職活動の実際などを語り合う懇談会は、毎年人気を集めている。
学生が受け入れ企業で就労体験するインターンシップ。2016年夏期は95社の協力を得て、176人の学生が参加した。事前にビジネスマナー講座を、事後には自らの体験を振り返るグループワークと企業の担当者を交えた成果報告会を行い、体験を実にしていく。
同センターは学生の状況に合わせたサポートの手厚さでも定評がある。試合や練習が多い体育会系クラブに所属する学生には、昼休み時間を使って各種研修を行っている。また、教員とも密に連絡を取りながら一人たりとも余すことなく状況を把握し、就職につなげる努力を行っており、2016年度の進路把握率は全卒業生の99.3%を誇る。
同センターは、今年9月に完成予定の「iCommons(アイ・コモンズ)」内に移転することになっている。同センター所長の北居明経営学部教授は「学生が集まる場でキャリア支援のセミナーなどに気軽に参加できる雰囲気をつくることで、より関心を高めていきたい」と話している。
創立100周年記念「iCommons」誕生へ 垣根越えた出会いを誘発
 9月に完成する「アイ・コモンズ」。学生の無限大の可能性を引き出す新施設として期待が高まっている
学園創立100周年を記念して、岡本キャンパスに地下1階地上4階の新たな複合施設「KONAN INFINITY COMMONS(iCommons=アイ・コモンズ)」が誕生する。かつて食堂や学生会館などがあった福利厚生エリアを再開発し、現在9月の完成に向け建設が進んでいる。
9月に完成する「アイ・コモンズ」。学生の無限大の可能性を引き出す新施設として期待が高まっている
学園創立100周年を記念して、岡本キャンパスに地下1階地上4階の新たな複合施設「KONAN INFINITY COMMONS(iCommons=アイ・コモンズ)」が誕生する。かつて食堂や学生会館などがあった福利厚生エリアを再開発し、現在9月の完成に向け建設が進んでいる。
建物に入ると、4階までの吹き抜け空間を利用した多目的スペース「Agora」があり、大型ディスプレーを活用したイベントやプレゼンテーションなどが開催できるようになっている。「Agora」を取り囲むように設けられた食堂は約1300席分あり、ワンフロアの席数としては国内の大学で最大級。食事以外の時間帯はスペースを区切ってさまざまな目的で利用できる。1年次に全学部の学生が交じって受講するプロジェクト型授業「共通基礎演習」もこのスペースで開かれる予定になっている。
3階は、ミーティングや成果発表会などに活用できる複数のプロジェクトルームがあり、ガラス壁にすることで活動を可視化し、融合や創発を促していく。またクラブの部室前のスペースを多く取ってクラブ間の交流を促進するようにしている。最上階の4階にはブックカフェ「TSUTAYA BOOK STORE」が入る予定で学生の人気を集めそうだ。また調理器具の充実したキッチンや、創作活動ができるアトリエなどのユニークな施設も備わっている。
学長室次長の林正樹さんは「人物教育のクオリティー・リーダーを目指す甲南新世紀ビジョンを実現するための施設。学部やクラブを超えて、また大学という枠を超えてさまざまな人たちが交わることのできる設備、機能を備え、新たな出会いや発見を誘発して学生の無限大の未来を広げたい」と完成後の役割に期待を寄せている。
学長に聞く
人物教育の率先が使命
 長坂悦敬学長
長坂悦敬学長
―2019年に学園創立100周年を迎えます。
このほど次の100年に向けた「甲南新世紀ビジョン」を定めました。建学の精神「人物教育の率先」の使命を果たし続けるべく「圧倒的な教育力により、人物教育のクオリティー・リーダーと呼ばれる存在になる」「世界に通じる特色ある研究力が教育に浸み出し、地域と連携して発展していることが社会に評価される大学になる」「融合力を発揮し、さまざまな環境変化に対応できる力、持続的に発展できる力を備えた大学になる」が三つの柱です。
―ビジョン実現へ具体策は。
学生数約9千人の「ミディアムサイズの総合大学」の強みを生かし、「学問分野の広がりを保ちながら隅々まで行き届く質の高い教育」「学部を超えて集う人が自然に交じり融合するキャンパス」という環境の下、さらに磨きをかけていきます。実現には、能動的学習を促す「場」、そこに参加しようと思わせる「誘発する仕掛け」、そして学生一人一人が自らの成長を確認できる「可視化」が重要なキーワードだと考えています。
―今年9月には「場」の一つとなる「KONAN INFINITY COMMONS(iCommons=アイ・コモンズ)」が完成します。
岡本キャンパスの文系ゾーンと理工系ゾーンの境目に位置し、学部やクラブの枠を超えて学生や教職員が自然に交わる空間となっており、互いに触発され創造力を生み出す「キャンパスの結節点」を目指しています。ここで展開される主体的な学びで獲得した行動知は、社会に出てから必要な突破力につながると考えています。人物教育のクオリティー・リーダーを目指し、進化を続けていきます。
在学生からのメッセージ
積極的な自分に大変身
マネジメント創造学部3年 原智美さん(20)
 人前に立って話すことが苦手だった自分を克服しようと、自ら考え、行動する力が習得できるマネジメント創造学部を選びました。主体的に学び、調べ、発表を繰り返す2年間で見違えるように自分が変わりました。また、日本語を使えない英語の授業でどうにか相手に伝えようと努力した経験は、カナダでの1カ月間の留学で役立ちました。「神戸ファッションウィーク」に関わるイベントの企画、運営など学外の活動にも参加し、その経験から明確になった進路を目標に、これからも積極的に学び続けていきます。
人前に立って話すことが苦手だった自分を克服しようと、自ら考え、行動する力が習得できるマネジメント創造学部を選びました。主体的に学び、調べ、発表を繰り返す2年間で見違えるように自分が変わりました。また、日本語を使えない英語の授業でどうにか相手に伝えようと努力した経験は、カナダでの1カ月間の留学で役立ちました。「神戸ファッションウィーク」に関わるイベントの企画、運営など学外の活動にも参加し、その経験から明確になった進路を目標に、これからも積極的に学び続けていきます。
大学概要
| 住所 | 岡本キャンパス=神戸市東灘区岡本8の9の1
西宮キャンパス=西宮市高松町8の33 ポートアイランドキャンパス=神戸市中央区港島南町7の1の20 |
|---|---|
| アクセス | 岡本=阪急岡本駅徒歩10分
西宮=阪急西宮北口駅徒歩3分 ポートアイランド=ポートライナー京コンピュータ前駅徒歩4分 |
| 学部(本年度定員) | 文学部(400人)、理工学部(155人)、経済学部(345人)、法学部(345人)、経営学部(345人)、知能情報学部(120人)、マネジメント創造学部(180人)、フロンティアサイエンス学部(45人) |
| 教員 | 教授196人、准教授56人、講師23人、助教4人 |
| 在学生 | 9080人(男子5369人、女子3711人) |
| ホームページ | http://www.konan-u.ac.jp/ |
オープンキャンパス スケジュール
| 日程 | 7月16日(日)、8月6日(日)、10月1日(日) |
|---|---|
| 時間 | 午前10時〜午後4時(10月1日のみ午前10時〜午後4時、正午〜午後4時) |
| お問い合わせ | 入試センター ☎︎078-435-2319 |